7,000個以上のNFTが21時間で完売。
ユーザーに寄り添うコミュニティ運用で売上獲得を後押し

株式会社GALLUSYS
https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYS
https://gallusys.com/

非言語写真SNSアプリ「ピクティア」をはじめ、のちに文化となるようなプロダクトの創造を目指す株式会社GALLUSYS(ガルシス)。シンセカイテクノロジーズでは、同社が開発した、スマホカメラを活用したGame-Fi(※)プラットフォーム「SNPIT(スナップイット)」のコミュニティ運営を支援しています。
※ゲーム(Game)と金融(Finance)の組み合わせた造語。ゲームにDeFi(分散型金融)の要素を掛け合わせたブロックチェーンゲーム全般を指す。
目的
SNPITユーザーとの繋がりを強化
NFT販売をコミュニティ運営で後押し
多様なコミュニティユーザーのフォローとマネジメント
課題
コミュニティの設計・運用経験がない
少人数でプロダクト開発にあたるため、ユーザーへの対応時間が限られる
グローバルユーザーにも対応したコミュニティづくり
効果
企業がプロダクト開発に専念できる環境を提供
7,000個以上のNFTを21時間で販売
登録者数は1万3,000人を超え、グローバル展開も視野に
・株式会社GALLUSYS代表 大塚様
・「SNPIT」コミュニティマネージャー Yuya
・株式会社SHINSEKAI Technologies COO 加藤

──「SNPIT(スナップイット)」の概要を教えてください。
大塚様:SNPITは、「Snap to Earn(スナップ・トゥ・アーン)=撮ることで稼ぐ」のコンセプトのもと、スマホカメラを活用してGame-Fiに参加できるサービスです。
ユーザーは、自身のカメラNFTで写真を撮影をすることで独自のトークンを獲得します。ゲームで獲得したトークンは、カメラの性能の向上やアプリ内の写真コンテストへの参加権として使えるほか、アプリ内で仮想通貨ポリゴン(MATIC)にも交換可能です。
──SNPITはどのような経緯から生まれたのでしょうか?
大塚様:開発のきっかけは、ランニングやウォーキングによって仮想通貨を稼げるブロックチェーンゲーム「STEPN(ステップン)」を知ったことでした。
通常、ブロックチェーンゲームは「ウォレット(仮想通貨を保管する電子財布)」の作成をはじめとする初期設定がハードルとなり、多くの人がプレイを諦めてしまいます。そんな中でSTEPNは、ゲーム自体の分かりやすさや面白さから、Game-Fi初心者の方にも受け入れられていました。
ちょうどカメラアプリ「ピクティア」を運営中だった私たちは、ウォーキングと同じくらい身近な「スマホでの写真撮影」が、Web3への新たな入口になりうると思い、SNPITの開発に踏み切りました。
──SNPITの普及により、大塚さんはどのような社会を目指しているのでしょうか?
大塚様:根底には「労働=時間の切り売り」という価値観を変えたいという想いがあります。
これまで多くの人は自分の時間を売ることで資本を得てきました。しかし、デジタルの世界では時間ではなく「どれだけクリエイティブな価値を創造したか」が資本になります。
──当社に、SNPITのコミュニティ設計・運用を依頼された理由を教えてください。
大塚様:当時は仮想通貨市場が低調な「冬の時代」。多額の開発費をかけて事業が継続できなくなる企業もあったため、コストはできる限りミニマムに抑えるつもりでした。
そんな背景もあり、事業構想時からアウトソーシングできる部分はプロに依頼し、自分たちはプロダクト開発に集中することを決めていました。
──コミュニティ設計・運用において重視したポイントを教えてください。
加藤:大きく2つあります。
まずは、カメラNFTの販売による売上の確保です。今年はSNPITトークンが上場して売上が立つことが見込まれたため、マーケティング視点も取り入れながら最大限の成果が得られるような施策を試みました。
次に、コミュニティ運営においてはアクティブユーザーやロイヤルユーザーを増やしつつ、それらのユーザーの声に対応する仕組み化が必須でした。
特にSNPITの場合、プロダクト開発に意見をくださるユーザーが初期段階から大勢いらっしゃいました。彼らの声を拾い適切に対応するためにも、コミュニティ内の体制を早急に整える必要がありました。
そこで、私たちが運営するコミュニティ人材ネットワーク「nest」から、Web3コミュニティの運用実績があるYuyaさんを抜擢。SNPITのモデレーターを経てマネージャーへと役割を変更し、コミュニティ管理に尽力してもらいました。
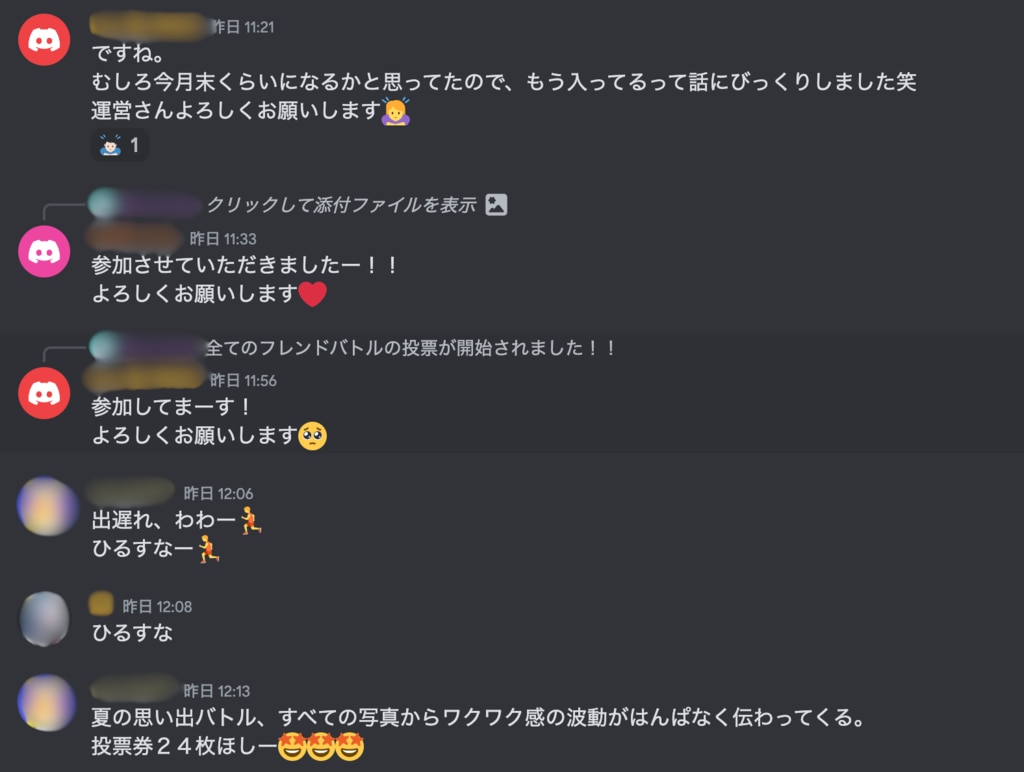
──コミュニティマネージャーとして、どのような点を意識して運営をされていますか?
Yuya:SNPITユーザーの中には、ブロックチェーンゲームを初めて体験する方やNFTへの知識が浅い方も一定数いらっしゃるため、細やかなサポートを心がけています。最近では、私が介入せずともユーザーの質問に回答したり、SNPITの良さを自主的に発信したりするKOC(Key Opinion Consumer)が増えています。

──2023年10月に初めて、NFTカメラのパブリックセールが行われました。結果はいかがでしたか?
大塚様:当初は1週間の販売期間を見込んでいたところ、開始から21時間で7,000個以上が完売し、想定以上の結果となりました。実は「コミュニティ立ち上げと同時のNFT販売は、早すぎるから売れない」という声も多くいただいていました。
それでも販売に踏み切ったのは、私自身がステークホルダーへの営業活動の中で、一定の手応えを感じていたからです。NFTの販売に関しては、表に見えない情報も加味しながら意思決定をしたため、コミュニティメンバーを不安にさせたかもしれませんね。
一方で、大塚さんが水面下で精力的に活動する様子も知っていました。地道な営業活動に加えて、アンバサダーの起用などが起爆剤となり、コミュニティの盛り上がりは一気に加速。プロダクト開発・営業活動・コミュニティ運用すべてが相乗効果を生み、良い結果に結びついたと感じています。
──当社の支援を通して、良かったと感じる点があれば教えてください。
大塚様:やはり、ブロックチェーンゲームには欠かすことのできない、コミュニティの設計・運営を一任できた点は大きかったです。現在、公式Discordの登録者数は1万3,000人、LINEのチャットグループは830人を超えていますが、自分たちだけではこれほどのコミュニティを運営できなかったと思います。
──当社の支援に対して率直なフィードバックをお聞かせください。
大塚様:まず、コミュニティ運営においてはユーザーのさまざまな要望に対して、臨機応変に対応してくれている点をありがたく感じています。
Yuyaさんが仰った通り、SNPITのコミュニティにはブロックチェーンゲーム初心者の方がいらっしゃる一方で、「プロダクト愛」が非常に高い方もいます。彼らは開発に対する要求も高いため、運営側には高度な専門知識と対応能力が引き続き求められると感じています。
その反面で、コミュニティを長く続けるには「新陳代謝」も必要です。専門性の高いメンバーに対応しつつ、いかに新しいユーザーを集め調和していくかが今後のコミュニティ運営の課題となるでしょう。
──SNPITの今後の展開について教えてください。
──シンセカイテクノロジーズとしては、今後どのような支援をしていきたいですか?
加藤:大塚さんが仰ったように、今後は事業フェーズにあわせてユーザー層も変化します。特にグローバルユーザーの増加は避けては通れないので、海外ユーザーもマネジメントできる運営体制を並行して整えるつもりです。
具体的には、英語ネイティブのコミュニティマネージャーを起用し、私たちが培ってきた「コミュニティマネジメントグロースモデル」を海外向けに転用します。
競合他社では真似できない、当社の強みを活かしたサービスを通して、SNPITのグローバル展開に貢献していきたいですね。

SNPITは、スマホカメラを活用した画期的なGame-Fi体験を提供する、世界初のSnap to Earnサービスです。より手軽にGame-Fiに参加できるエコシステムを目指し、スマートフォンカメラという普遍的な機能を活用しています。
ユーザーは、カメラNFTを活用して撮影を行い、それにより独自のトークンを獲得できます。さらに、トークンを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、トークン獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるトークン獲得も可能です。
SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。
公式Whitepaper: https://wp.snpit.xyz/
会社名:株式会社GALLUSYS
所在地:東京都新宿区西新宿3丁目2番9号
代表者:大塚敏之
設立:2020年9月
事業内容:システム開発
株式会社GALLUSYSホームページはこちら
https://gallusys.com/
© SHINSEKAI Technologies 2024.